-
九谷の“オーバースペックさ”に魅かれ。
職人技工への憧れと再評価。
- 秋元:高さんは大阪芸術大学を出られていますが、ご専攻は?
高:もともと美術学科に入っています。初代が「うちの工房には絵の描けんやつはいらんからな」と常々言っていて。僕自身絵を描くのが好きだったので、絵で入ったのですが、入学してみたら今度は工芸の方が面白くなってきて。工芸の先生に山田光先生はじめ、京都の「走泥社(※)」の方がたくさんおいでたんです。なので、途中から工芸の方に転向しています。
(※)走泥社…1948年に京都で結成された陶芸家のグループ。1998年に解散するまで50年の長きにわたり活動。戦後の陶芸界を代表する作家たちも多数所属した。

-
秋元:ああ、そうでしたか。走泥社の先生方に教わる中で、造形的なセンスを磨いていかれたのだと思うのですが、その中で家業や九谷焼の見え方に、何か変化はありましたか?
高:気持ち的には「やっぱり九谷焼が一番いいなぁ」と思いながら、京都的な手仕事をしていました。九谷焼の細部にこだわる感じは、走泥社の精神に通ずるところがあるような気がしていて。特に山田光先生の授業にはかなり影響を受けましたね。
 器を埋め尽くすように細やかな仕事がなされた九谷焼。
器を埋め尽くすように細やかな仕事がなされた九谷焼。-
秋元:高さんは色々と展覧会も出されていますけど、今ってそういった作品制作と、商品としての制作の割合はどのくらいなんでしょう?
高:僕はもう、公募展に出すの辞めたんですよ。
秋元:そうでしたか。それはまたどうして?
高:私の場合はと前置きすると、家の仕事と、例えば日展に出す作品というものが、全く違うというかむしろ真逆なので。なんというか 、その都度“人間”を変えないといけないんですよ。毎度それをやるのが辛くて。大学の頃はよかったんですが、家の仕事をやるようになって「どちらを極めるか」と考えたときに、僕は代々からの仕事を選びました。

-
秋元:確かに、日展って基本的には近代美術のフレームなので、その並びで工芸を考えると“芸術工芸”ということになりますもんね。そこで言う “芸術”というのは、“=個性”というか「人のやっていない表現をしているか」ということになってくる。その中では職人技術というものはどちらかというと評価されにくい項目ではありますからね。
高:はい、僕もそれを意識して制作するんですけど、どうしても作品に“家の仕事”がでちゃうんです。審査員の先生方にはそういうところをズバッと突かれるんですよね(笑)。
だから、僕は日々やっていることが繋がって完成度を上げていくというようなことをしたいなと。肩書きは必要ないので、今はただ「名人」になりたいなと思っています。
秋元:ご自身の中で、そんな風に決着つけられたわけだ。

-
秋元:今まで高さんのお話を聞いていると、根底にずっと“九谷焼への愛” みたいなものを感じるのですが、嫌になったことなどはなかったんですか?
高:僕は九谷焼のオーバースペックな感じが好きなんです。若い頃に「真っ白な器にちょっとだけ描く方が良いのかもしれない」と、2〜3年浮気したことも一度ありましたが(笑)。大学時代には沖縄のやちむんの窯に行ったり、備前に行ったり、いろんな産地の美意識にも触れてはいるのですが、最終的には九谷のこの“過剰さ”に魅かれているんです。
秋元:今また「九谷の過剰な装飾が面白い」という時代になってきていますよね。 “技巧”や“上手さ”といったものへの憧れというか。でも、ちょっと前までの九谷焼って一時「見向きもされない」というか、もはや「忘れ去られた」というような時代がありましたよね。
高:ありました、ありました。デパートの売り場で奥様方が「私、この九谷焼のピカピカしたの大っ嫌い!」って話されているのを耳にしたこともあります(笑)。その頃って、モノクロの食器や素朴な土ものが流行った頃で、それはもう九谷焼とは正反対のものじゃないですか。なんとかしようと形を変えたり、色合いを変えたり。「辛いなー」と思いながら、売れない間は色々やってましたが。

-
秋元:九谷焼が再評価され出したのって、本当ここ何年の話ですもんね。先ほど制作されていた獅子のような「型もの」だって、今改めてみると面白いんですけど、全然売れない時代があったでしょうし。
高:はい。「獅子!? 今なんで獅子!?」みたいな感じでした(笑)。今やっと再評価されてきているのはありがたことですが、時代はまた変わるので、そこに対応していくために色々考えておかないといけませんね。

-






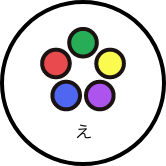


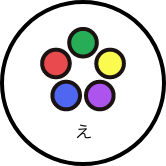


 器を埋め尽くすように細やかな仕事がなされた九谷焼。
器を埋め尽くすように細やかな仕事がなされた九谷焼。


